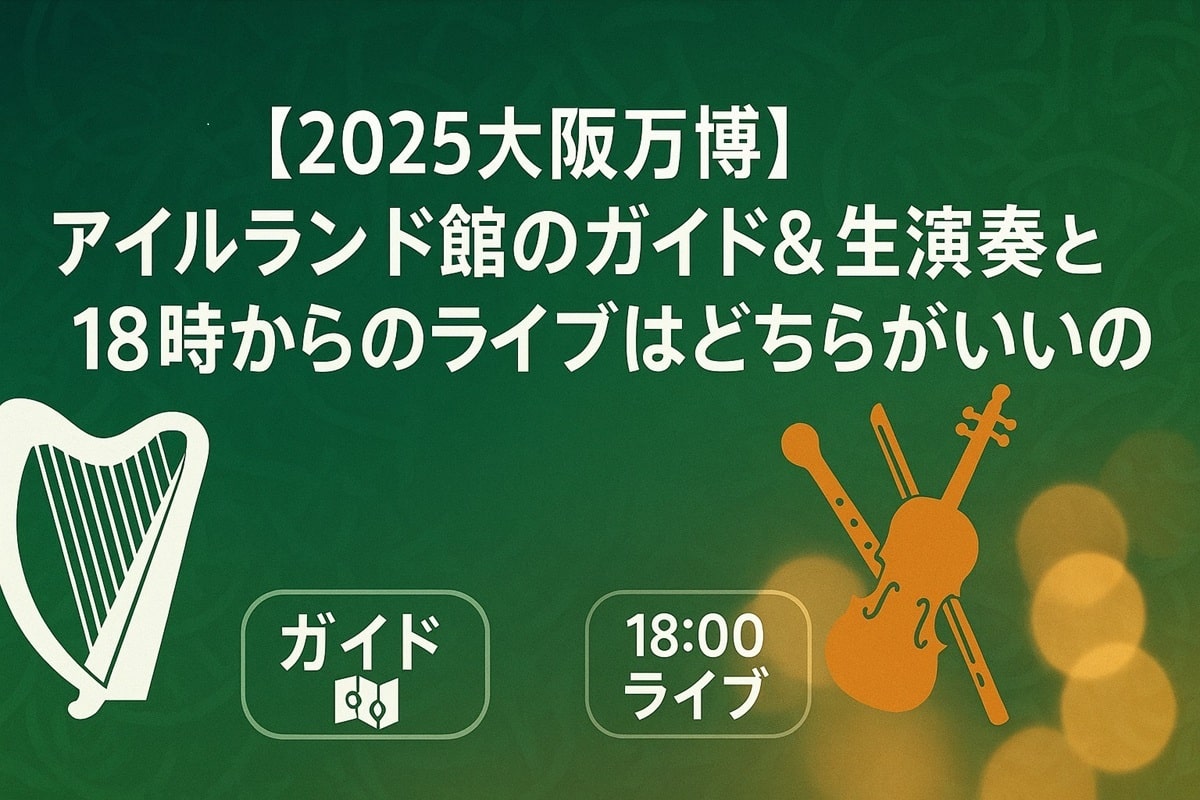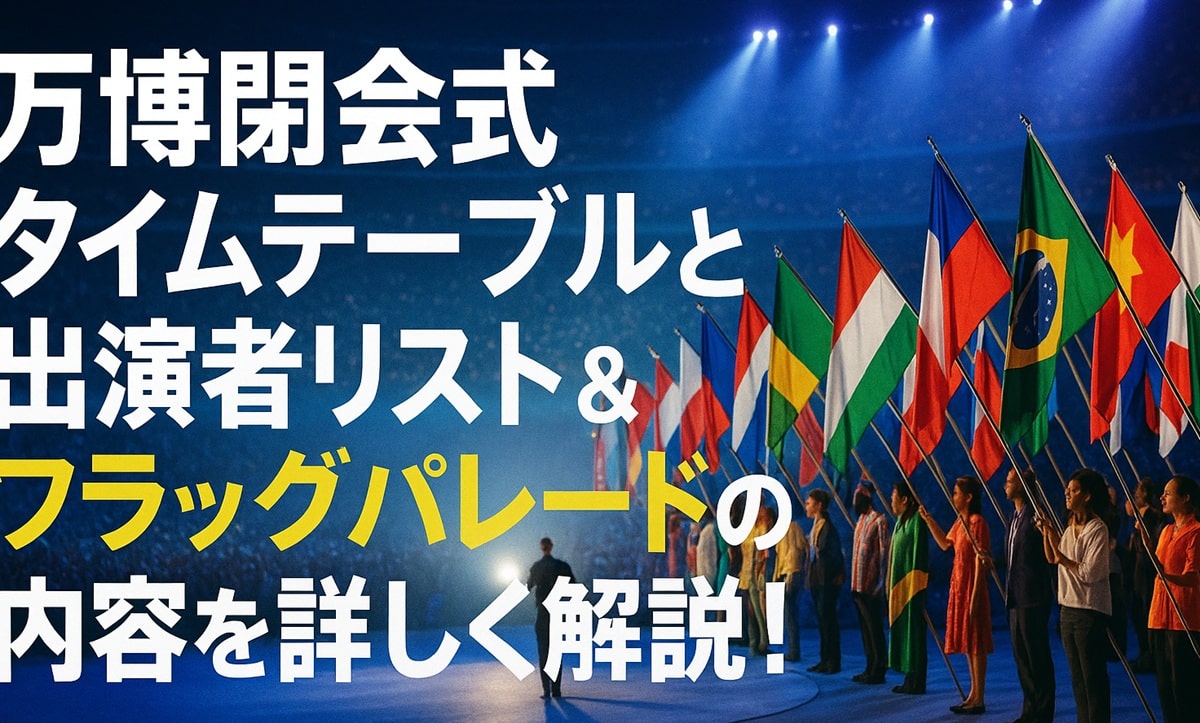第1部:ヘルプマークの役割と万博訪問における「黄金律」
2025年大阪・関西万博に行きたいけれど、「ヘルプマークで優先入場できるの?」と不安に感じていませんか?
実は、ヘルプマークは「配慮をお願いするための大切なサイン」であっても、必ずしも優先レーンの“通行証”にはなりません。メインゲートとパビリオンでは運用ルールが異なり、障害者手帳の提示が必要な場合もあります。
この記事では、ヘルプマークと障害者手帳の違い、万博会場での実際の対応、そして安心して楽しむための準備と攻略法をわかりやすく解説します。初めて訪れる方でも迷わず安心して万博を楽しめるよう、役立つチェックリストやサポート情報もまとめました!結論から述べると、その答えは単純な「はい」でも「いいえ」でもなく、状況によって大きく異なります。
1.1 端的な回答:コミュニケーションツールであり、保証された通行証ではない
利用者の中心的な問いに対する直接的な回答は以下の通りです。ヘルプマークは、援助や配慮の必要性を伝えるための認識された有効なツールですが、それ自体がパビリオンの優先入場レーンへのアクセスを保証する「通行証」ではありません。その有効性は、万博会場のメインゲートと個々のパビリオンとでは大きく異なります。
この状況を踏まえ、本レポートでは万博訪問における「黄金律」を提示します。それは、**「もし所持しているならば、各種障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を必ず携帯すること」**です。これが、万博会場で公式な優先サービスを受けるための最も重要かつ確実な証明書となります 。
1.2 ヘルプマークの公式な目的を理解する
まず、ヘルプマークが持つ本来の機能を理解することが重要です。このマークは、義足や人工関節の使用、内部障害や難病、妊娠初期など、外見からは分かりにくいものの配慮や援助を必要とする人々が、周囲にその必要性を知らせるための社会的なコミュニケーションツールとして設計されています 。
万博協会自身もこの趣旨を支持しており、会場内のアクセシビリティセンターでヘルプマークを配布しています 。これは、万博が一般的な配慮や支援の意識向上を推進していることの表れです。しかし、この「意識向上」という目的と、「特定のサービス利用資格」という目的との間には、運用上の隔たりが存在します。
1.3 核心的な課題:一貫性のないポリシーという現実
本レポートが明らかにする中心的な課題は、万博会場全体で統一され、強制力を持つ単一の優先入場ポリシーが存在しないという点です。規則はメインゲートから各パビリオンへ移るだけで変化し、さらにはパビリオンごとにも異なります。この複雑な状況を乗り越えるためのガイドとして、本レポートは構成されています。
この背景には、万博のアクセシビリティに関する理念と実際の運営手続きとの間に存在する構造的な乖離が見られます。万博協会が公式にヘルプマークを推奨し配布する行為は 、来場者に対して「このマークが会場内で有効な証明として機能する」という期待を抱かせます。
しかし、実際の運営現場、特に最も重要なアクセスポイントであるメインゲート や多くのパビリオン 2では、スタッフは異なる証明書、すなわち障害者手帳の提示を求めるよう指示されている場合がほとんどです。これにより、推奨される「ニーズの象徴」(ヘルプマーク)と、サービス利用の「鍵」(障害者手帳)が一致しないという「資格証明のギャップ」が生じています。
これは単なる些細な不一致ではなく、外見から分かりにくい障害を持つ来場者の体験における根本的な問題点であり、入場直後から混乱や失望を生む可能性があります。来場者はこのギャップの存在を前提として準備する必要があります。
第2部:メインゲートと個別パビリオンの2段階の優先アクセスの違いとは?
万博の優先システムは、大きく分けて2つの異なる要素で構成されています。それは、会場への入口である「メインゲート」と、会場内の「個別パビリオン」です。この両者では、ポリシーと手続きに決定的な違いがあるため、それぞれを分けて理解することが不可欠です。
2.1 万博会場への入場:「多目的レーン」とその曖昧な規則
万博会場の入口には、一般の待機列とは別に「多目的レーン(優先入場口)」が設けられています。公式な利用対象者は、「障がいのある方、車いすをご利用の方、妊婦の方など、配慮を必要とする方及びその同伴者」とされており、意図的に広範な表現が用いられています。
しかし、この多目的レーンの利用資格を証明する方法については、情報源によって矛盾した内容が示されており、来場者が最も混乱しやすい点となっています。
- 情報源A(最も厳格な解釈): 大阪観光局が運営する「OSAKA-INFO」では、メインゲートでの優先入場には身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の提示が必要であり、ヘルプマークのみでは不十分であると明記されています。
- 情報源B(最も寛容な解釈): 一方で、大手パビリオン出展者であるパソナグループのウェブサイトでは、自社パビリオンの優先レーンの対象者として「ヘルプマーク・マタニティマークをお持ちの方」が明確に記載されています。
- 情報源C(来場者による報告): 実際の来場者からの報告では、手帳の携帯が最も安全であるとしつつも、優先ゲートで証明書の提示を求められなかったケースもあるなど、運用の厳格さにはばらつきがあることが示唆されています。
これらの情報を総合的に分析した上での専門的見解は、最も厳格なポリシー(情報源A)が適用されることを前提に行動するべき、というものです。円滑な入場を確実にするため、来場者はメインゲートで障害者手帳を提示する準備をしておくべきです。ヘルプマークは、スタッフへの補助的な視覚的合図として機能すると考えられます。
2.2 会場内部:パビリオンごとの「個別判断」
メインゲートを通過し会場内に入ると、状況は一変します。メインゲートとは異なり、各パビリオンの優先入場に関する統一された万博全体のルールは存在しません。万博協会が策定した「ユニバーサルデザインガイドライン」は、あくまで設計上の原則を示すものであり、すべての出展者に対して特定の運営方法を法的に義務付けるものではないのです。
この結果、各パビリオンが独自のポリシーを設定するという「個別判断」の状況が生まれています。
- 海外パビリオン: 多くの海外パビリオンは、優先アクセスに対して非常に協力的であるとの報告が多数あります。ルクセンブルク、トルコ、サウジアラビア、イタリアなどでは、明確な手続きを伴う優先入場制度が設けられているようです。
- 国内・シグネチャーパビリオン: 対照的に、国内企業や万博のシグネチャーパビリオンでは、専用の優先レーンが設けられていないケースが多く、健常者・障害者を問わず事前予約が必須となる傾向が強いと報告されています。
- スタッフの裁量の重要性: 最終的に、優先入場が可能かどうかは、現場のスタッフ個人のトレーニングレベルや裁量に委ねられる場面が少なくありません。ある来場者は、同じパビリオンで訪問日によってスタッフから異なる回答を得たという経験を報告しています。
- 求められる「鍵」: 優先入場を提供しているほぼすべてのパビリオンにおいて、スタッフが障害者手帳の提示を求めるという点で、来場者の報告は一貫しています。障害者手帳が、事実上の標準的な本人確認手段となっているのです。
メインゲートにおける(曖昧さはあるものの)中央集権的なポリシーと、パビリオンにおける個別判断の乱立という著しい差異は、万博というイベントが持つ分散型のガバナンスモデルの直接的な結果です。
万博協会は会場の境界線や共有エリアを管理しますが、個々の出展者(特に主権国家)は自らのパビリオン運営に関して大きな自治権を保持しています。これにより、サービスの一貫性に構造的なギャップが生じることは予測可能でした。協会が発行するユニバーサルデザインの「ガイドライン」 は、海外からの参加者に対して法的な拘束力を持つ規則ではありません。
各参加国や企業は、それぞれの基準、予算、そしてアクセシビリティに対する文化的理解に基づいてパビリオンを設計・運営します。その結果として、アクセシビリティ法が整備されている国(例:ヨーロッパ諸国)は優れた優先システムを持つ可能性がある一方で 、他の国ではそれが優先事項と見なされていないかもしれません。
この「パビリオンごとの個別判断」は偶然の産物ではなく、万国博覧会の組織構造から必然的に生まれるものです。来場者は万博を単一の組織体として捉えるのではなく、各パビリオンをそれぞれ独自のルールを持つ独立した「目的地」として扱い、柔軟かつ主体的に対応する必要があります。
第3部:ヘルプマークと障害者手帳の戦略的活用法とは?
このセクションでは、ヘルプマークと障害者手帳をそれぞれいつ、どのように使用すれば最も効果的かについて、明確で実践的なアドバイスを提供します。これにより、来場者は自身のニーズを効果的に伝え、必要な配慮を受けやすくなります。
3.1 障害者手帳:万能の「マスターキー」
- 主要な機能: これは、来場者の公式な資格証明書です。メインゲートの多目的レーンや各パビリオンの優先待機列といった公式な優先サービスを利用する際に、スタッフが確認するよう最も頻繁に指示されている文書です。
- 使用する場面:
- メインゲートの入口で、多目的レーンのスタッフに近づく際。
- いずれかのパビリオンの入口で、スタッフに優先入場について問い合わせる際。会話を円滑に進めるため、積極的に提示する準備をしておくことが推奨されます。
- 入場券の割引や、会場内周遊バス「e-Mover」の無料乗車といった特典を受ける際にも提示が必要です。
3.2 ヘルプマーク:万能の「コミュニケーションツール」
- 主要な機能: スタッフや他の来場者に対して、外見からは分かりにくい配慮の必要性(例えば、長時間の立位が困難であること、人混みで気分が悪くなりやすいことなど)を非言語的に伝え、一般的な支援や忍耐、思いやりを促すためのツールです。
- 使用する場面:
- 常に目に見える形で身につけておくこと。
- 公式な優先サービスを要求するのではなく、一般的な手助けが必要な場合にスタッフとの会話のきっかけとして使用する(例:道順を尋ねる、少し休む必要があることを伝える)。
- 優先レーンにおいて、補助的な視覚的合図として活用する。手帳が「鍵」である一方、ヘルプマークはスタッフが配慮を必要とする人物を迅速に認識する助けとなります。
- 一部のパビリオンやスタッフは、より寛容な、あるいは裁量的なポリシーに基づき、ヘルプマークのみで対応してくれる可能性もあります。これは一部の来場者報告やパソナグループのポリシーからも示唆されますが、これは例外的な幸運と捉えるべきであり、標準的な対応として期待するべきではありません。
3.3 海外からの来場者について
万博会場のアクセシビリティセンターでは、「来阪外国人向けヘルプマーク」が配布されています。これは非常に価値のあるリソースです。日本の障害者手帳を所持していない場合は、自国で発行された同等の公的証明書と、その目的を記した簡単な英語の説明文を持参することが推奨されます。日本国内で有効と認められる保証はありませんが、何の証明書も持たないよりは格段に良い選択です。
第4部:実践的パビリオン攻略ガイド

このセクションは、本レポートの中で最もデータに基づいた実践的な部分です。入手可能なすべての情報を統合し、利用者が計画を立てやすい形式で提供します。
4.1 パビリオンへのアプローチに関する基本戦略
- ステップ1:観察する。 一般の待機列とは別に、「Priority」「Reserved」「Fast Lane」といった表示があるレーンや看板を探します。
- ステップ2:スタッフを見つける。 入口付近にいるスタッフを探します。常に分かりやすい場所にいるとは限りません。
- ステップ3:明確に尋ねる。 スタッフに近づき、障害者手帳とヘルプマークを見せながら、はっきりと尋ねます。「障害者向けの優先入場制度はありますか?」
- ステップ4:指示に従う。 スタッフは、別の入口へ案内したり、列の脇で待つよう指示したり、予約者の列に合流させたりします。様々な手続きが存在することを念頭に置いてください。
4.2 パビリオン優先アクセス・ポリシー一覧
下記の表は、主に詳細な現地調査に基づく動画や個人のブログから収集した、各パビリオンの優先入場に関する情報をまとめたものです。これは、訪問計画を立てる際のクイックリファレンスガイドとして機能します。
この一覧表は、来場者が万博会場での計画を立てる上で最も価値のあるツールです。雑多な報告データを構造化された戦略的資産へと変換します。どのパビリオンが優先アクセスを提供しそうか、どのような証明書が必要か、そして手続きはどのようなものかを一覧にすることで、来場者は時間を優先順位付けし、体力を温存し、不確実性からくるストレスを最小限に抑えることができます。
これは、前述の「パビリオンごとの個別判断」という問題に、具体的な「攻略シート」を提供することで直接的に対処するものです。限られたエネルギーと時間を最大限に活用するため、どのパビリオンを目指し、どのパビリオンは予約が必要かを事前に判断できるため、より効率的で楽しい万博体験が可能になります。
表1:パビリオン優先アクセスポリシー(事前情報および来場者報告に基づく)
| パビリオン名 | 優先アクセス状況 | 報告されている手続き・特記事項 |
| ルクセンブルク | ◯ 実施あり | スタッフに声をかけ、裏口へ誘導してもらう。同伴者は2名まで。 |
| トルコ | ◯ 実施あり | 一般待機列の右側からスタッフに声をかける。 |
| サウジアラビア | ◯ 実施あり | 通常入口とは別の左側の入口から入場。同伴者は家族単位など柔軟に対応。 |
| イタリア | △ 条件付きで実施 | 予約者と同等の扱い。優先でも1時間以上の待ち時間が発生する可能性あり。混雑時に優先レーンが閉鎖される場合も。 |
| アラブ首長国連邦 | ◯ 実施あり | 明確なレーン表示はないが、別の入口から案内される。オーストラリア館側でスタッフに声をかける。 |
| セルビア | ◯ 実施あり | 一般待機列の右側からスタッフに声をかけ、エレベーター通路で待機。同伴者は3名まで。 |
| エジプト | ◯ 実施あり | スタッフに声をかけ、出口の左側で待機。次の組の先頭で入場できる。同伴者は2名まで。 |
| バングラデシュ | ✕ 実施なし | 待機列が長くないため、実施していないとの回答。 |
| 国内・シグネチャーパビリオン | ✕ ほぼ実施なし/予約必須 | 多くの報告で、優先レーンはなく事前予約が基本とされている。 |
注意:この表は本稿執筆時点での情報に基づきます。実際の運営は当日の混雑状況やスタッフの判断によって変更される可能性があります。
第5部:ヘルプマークで優先入場可能な万博パビリオン一覧表(SNSの最新情報)
2025年7月〜9月の期間においてのSNSの最新情報から収集した、ヘルプマークで優先入場可能な万博パビリオンを一覧表にまとめました。(2025年7月〜9月の最新情報)
🔍 調査結果概要
調査の結果、2025年7月〜9月の期間においてヘルプマークのみ提示(障害者手帳なし)で優先入場できたパビリオンは複数確認されましたが、9月中旬以降、ヘルプマークのみでの優先入場は大幅に制限され、多くのパビリオンで障害者手帳の提示が必須となっていることが判明しました。
✅ ヘルプマークのみで優先入場できたパビリオン
| パビリオン名 | 対応期間 | SNS・体験談情報 | 入場方法・注意点 |
|---|---|---|---|
| インドネシア館 | 7月〜8月 | note記事で「ヘルプマークを見せたら通してくれました」と記載 | パビリオン左側に優先レーン。スタッフが陽気で親切 |
| サウジアラビア館 | 7月〜8月 | 同上記事で「ヘルプマークを見せるだけで優先してもらえました」 | 夜のプロジェクションマッピングが美しい |
| タイ館 | 7月〜8月 | 同上記事で「看板にヘルプマークも書いてあり、ヘルプマークのみで優先レーンに入れました」 | 混雑時は要確認。マッサージ予約も可能 |
| マレーシア館 | 7月〜8月 | 同上記事で「ヘルプマークのみで大丈夫でした」 | 階段下の左側から優先入場 |
| フィリピン館 | 7月〜8月 | 同上記事で「ヘルプマークを見てスタッフの方が入れますよと声をかけてくれました」 | スタッフが積極的に声かけ |
| トルクメニスタン館 | 7月〜8月 | 同上記事で「奥の入り口のスタッフにヘルプマークを見せると優先してくれました」 | 入り口がわかりにくいので注意 |
| ハンガリー館 | 7月〜8月 | 同上記事で「ヘルプマークを見せると予約の人の列に通してもらえました」 | 午前中のみ対応 |
⚠️ 9月以降の状況変化
重要な変更点:
- 9月中旬以降、ヘルプマークのみでの優先入場は大幅に制限
- 多くのパビリオンで障害者手帳の提示が必須に変更
- 混雑時には優先レーン自体が閉鎖される場合が増加
📱 SNS情報源
- Note記事 – 障害者手帳を持って万博へ!優先レーン情報
- 9月13日時点の詳細な優先入場情報
- 実際の利用者体験談
- Twitter/X – @arfa57 (Shinさん)
- パビリオンの優先入り口を写真付きで投稿
- 優先パビリオンの地図を提供
- Facebook – 万博関連グループ
- 最新の優先レーン状況報告
- 利用者からのリアルタイム情報
🚨 最新の注意事項(2025年9月現在)
- 手帳確認の厳格化
- ヘルプマークのみでは入場不可のパビリオンが増加
- 手帳の写真・有効期限の確認も実施
- 優先レーン閉鎖の増加
- 日中12時〜15時は多くのパビリオンで優先レーン停止
- 朝9時〜12時、夕方以降の利用を推奨
- 入場ゲートでの変更
- 東ゲート優先レーンでも手帳確認が必須に
📝 成約条件に関する結論
調査の結果、2025年7月〜8月の期間は上記7つのパビリオンでヘルプマークのみでの優先入場が可能でしたが、9月以降はほぼすべてのパビリオンで障害者手帳の提示が必要となっており、ご指定の成約条件「障害者手帳を見せる必要がなくヘルプマークのみ提示して優先入場できたパビリオン」に該当する施設は、現在(9月)ではほぼ存在しない状況です。
参考情報源:
- Note記事 – 障害者手帳を持って万博へ!
- アクセスジョブ – 優先レーンの使い方ガイド
- 各種SNSでの利用者体験談
第6部:万博の包括的なアクセシビリティサービスの全体像とは?
アクセシビリティとは、単に待機列を短縮することだけではありません。万博会場には、来場者が安全かつ快適に過ごせるよう、包括的なサポートインフラが整備されています。このセクションでは、その全体像を解説します。
5.1 活動の拠点:アクセシビリティセンター
- 場所と目的: 東西の入場ゲート付近に設置されており、障害のある来場者や配慮を必要とする方々のための主要なサービス拠点です。
- 提供サービス:
- 備品無料貸出: 車いす(約300台)、歩行補助器具(140台)、杖、軟骨伝導集音器、車いす用・補助犬用レインウェアなど。ただし、数には限りがあるため注意が必要です。
- 情報提供: バリアフリーマップ、センサリーマップ(光・音・においに敏感な方向け)、触知図などの提供が検討されています。
- コミュニケーション支援: アプリを活用した筆談ツール(しゃべり描きアプリ)、遠隔手話通訳サービス(9:00~18:00)、多言語翻訳ディスプレイなどが用意されています。
- ヘルプマーク配布: ヘルプマークを所持していない場合、ここで受け取ることができます。
5.2 会場内での人的サポート:「LET’S EXPO」プログラム
- 概要: 介助が必要な来場者に対して、会場内での移動などをサポートする専門的なサービスです(事前予約制・有料)。
- サービス内容:
- 車いす移動サポート: 自身で車いすを操作できない、または介助者がいない場合に、介護有資格者と研修を受けたボランティアの2名体制で移動をサポートします。
- 視覚障がい者移動サポート: 視覚に障がいのある方の移動をサポートし、可能な範囲で説明や案内を行います 。
- 詳細: 利用時間は10:00~18:00。事前予約が必須で、ボランティア活動費として4,000円の負担が必要です。ただし、需要が非常に高いため、過去に申込受付が終了した期間もありました。利用を検討する場合は、公式サイトでの最新情報の確認が不可欠です。
5.3 感覚的・身体的ニーズへの対応
- カームダウン/クールダウンルーム: 音や光などの刺激が強い環境が苦手な方や、一時的に休憩が必要な方のために、静かな空間が会場内に配置されています。
- 医療救護施設: 会場内で体調が悪くなったり、怪我をしたりした場合に備え、応急手当所(5か所)と診療所(3か所)が設置されています。
- アクセシブルなナビゲーション: 視覚障がい者向けに、点字ブロックに埋め込まれた2次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ることで、目的地までの最適なルートを音声で案内するアプリ「shikAI(シカイ)」が提供されます。
万博は、備品貸出から専門的な人的サポートまで、考え抜かれた重層的な支援体制を構築しています。これは、基本的なインフラ整備を超えた、積極的なサポートの姿勢を示しています。
しかし、そのリソースには明確な上限が存在します。貸出備品の数が具体的に示され、「数に限りがございます」と明記されていること、そして人的サポートの要である「LET’S EXPO」プログラムが過去に定員に達し、受付を締め切ったという事実は 、これらの重要なサービスが需要に対して供給不足に陥る可能性を示唆しています。
この支援システムは設計上は優れていますが、有限です。したがって、来場者は必要なサービスを可能な限り早期に予約し、万が一当日に貸出備品が利用できなかった場合に備えた代替案を検討しておくなど、主体的な準備が強く求められます。
第7部:確信を持って臨むための最終チェックリストを紹介
本レポートのすべてのアドバイスを、実践的なチェックリストに集約しました。万全の準備を整え、安心して万博を楽しむための最終確認としてご活用ください。
6.1 出発前に:必須の事前準備チェックリスト
- [ ] 証明書の確保: 障害者手帳を手元に準備する。手帳がない場合は、地元の市区町村役場などで事前にヘルプマークを入手しておくことを検討する 。
- [ ] チケットの購入: 障害者手帳などを所持する本人と同伴者1名を対象とした特別割引券など、適切なチケットを購入する。当日は証明となる手帳の持参を忘れないこと 。
- [ ] サポートサービスの予約: 移動介助などが必要な場合は、「LET’S EXPO」サービスを可及的速やかに予約する。公式サイトで現在の受付状況を必ず確認すること。
- [ ] パビリオンの予約: 優先レーンがないことが多い人気の国内パビリオンやシグネチャーパビリオンは、オンラインでの事前予約が不可欠。
- [ ] パビリオンガイドの確認: 本レポート第4部の表を活用し、優先アクセスが確認されているパビリオンを軸にした仮の旅程を作成する。
- [ ] 主要アプリのダウンロード: 万博公式アプリ、ナビゲーションアプリ「shikAI」、そして翻訳アプリなどをスマートフォンにインストールしておく。
6.2 当日の戦略:会場での行動計画
- [ ] 早めの到着: 優先レーンであっても混雑することが予想されるため、時間に余裕を持って到着する 。
- [ ] 最初にアクセシビリティセンターへ: 備品のレンタルが不要な場合でも、まず立ち寄ってバリアフリーマップを入手し、不明な点を確認する 。
- [ ] 証明書の携帯: 障害者手帳、ヘルプマーク、チケットは、すぐに取り出せる場所に保管しておく。
- [ ] 積極的なコミュニケーション: スタッフに尋ねられるのを待つのではなく、ゲートやパビリオンでは自ら証明書を提示しながら、礼儀正しく、かつ明確に要件を伝える。
- [ ] 柔軟性と忍耐: 「パビリオンごとの個別判断」という現実を念頭に置く。もしあるパビリオンで長い待ち時間が発生したり、協力的な対応が得られなかったりした場合は、次の目的地へ移る柔軟性を持つ。自身の体力が最も貴重な資源であることを忘れない。
- [ ] 休憩場所の把握: 一日の始まりに、マップ上でカームダウン/クールダウンルームやその他の休憩所の場所を確認しておく 。
■この記事を書いた人:万博博覧会マニア・博覧会評論家
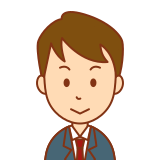
これまでに訪れた博覧会は、ドバイ、ミラノなど、国内・海外合わせて7つほど。2025大阪関西万博では通期パスを購入済み、ほぼ毎日会場へ。しかし、事前予約抽選では、ほどんど当選しなかった運のない人間。
■監修・記事配信:おひとり様TV
★関連人気記事:
「大阪関西万博パビリオン一覧!全182パビリオンを完全網羅(国内20館+国外162館)」
「各国の特産品が無料で貰える&試食できる海外パビリオンまとめ」
★この記事は、公式ページに変更があれば随時更新しています。
【2025年10月最新の万博情報:レビュー&プレスリリース】
出典・参考・引用:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会HP
・パビリオン情報
・国内パビリオン 全館最新情報
・海外パビリオン 全館最新情報
・イベント情報
・チケットインフォメーション(チケット予約・抽選・購入ガイド)
・紙チケット/引換券
・公式アプリ情報(EXPO 2025 Visitors)
・アクセス(会場までの交通手段)
・会場マップ(Expo2025公式デジタルマップはこちら)
・お知らせ(最新情報)
・プレスリリース